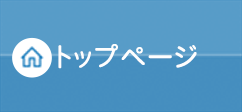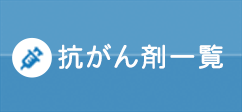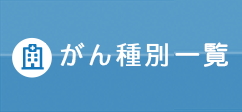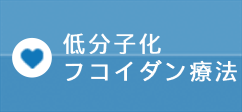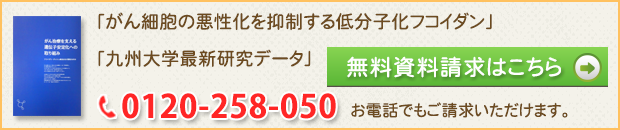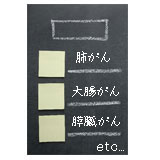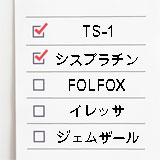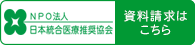膵臓は肝臓や十二指腸、胃などの消化器の最も深い場所に存在するため発見が難しく、初期の段階ではほとんど症状が出ることもありません。そのため、症状が出た時点で検査して診断された時には進行し、治療が困難な場合がほとんどです。
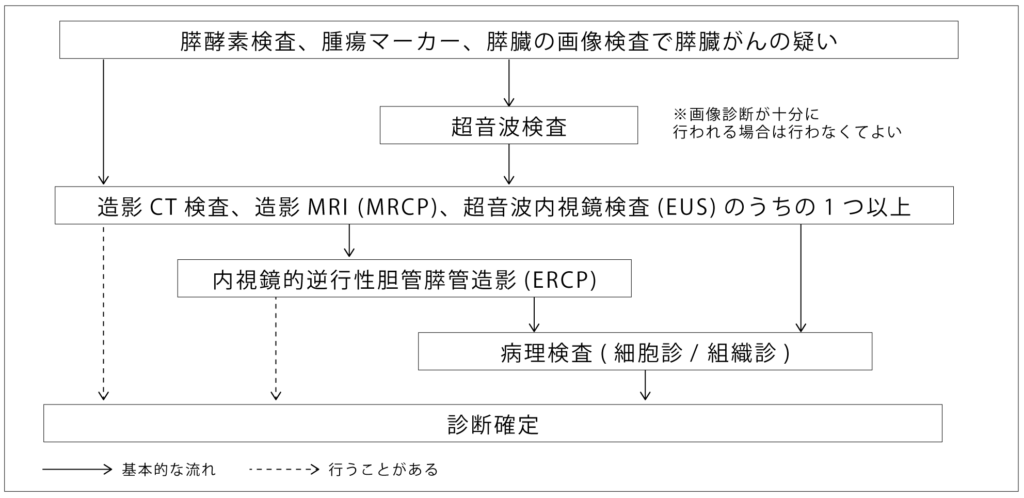
膵臓がんの検査方法
膵臓がんが疑われる場合、膵臓がんと確定するためにCTなどの画像検査に加え、膵臓の組織を採取して顕微鏡でみる病理検査も行われます。
これらの検査を組み合わせながら、総合的に膵臓がんと診断されます。
1)血液検査
血液検査は、血液中のアミラーゼ、リパーゼ、エラスターゼ1といった膵酵素と腫瘍マーカーであるCA19-9、CEAなどの数値が上昇していないかを調べます。また、治療中も抗がん剤の治療効果を調べるために毎月血液検査が行われます。
| マーカー名 | 基準値 |
|---|---|
| CEA | 5以下 |
| CA19-9 | 37以下 |
| Span-1 | 30以下 |
| DUPAN-2 | 150以下 |
2)腹部超音波検査(エコー検査)
腹部超音波検査は、腹部に超音波を発信するプローブを当てて、そこから返ってくる反射波(エコー)をコンピューターで画像化します。また、胃や食道の内視鏡検査も行い、胃炎や胃潰瘍、胆石などの一般的な消化器の病気の有無も調べます。
3)MRI検査
強力な磁力と電波を使用した検査方法で、体内のさまざまな方向の断面を画像化し、がんと正常組織を区別して映し出します。MRI検査は病変の有無だけでなく、広がりや多臓器への転移を確認することができます。
●MR胆管膵管撮影(MRCP)
MRIを撮影し、コンピューターを使って胆管や膵管の状態を詳しく調べる検査です。内視鏡や造影剤を使わずにERCPと同じような画像を作れるので、ERCPの代用として行われることが多くなってきた検査です。
4)CT検査
X線を体の周囲から当てて、体の断面を画像化する検査で、がんの有無や広がりを確認するために行われます。膵臓がんでは、がんの形や位置を細かく映し出すために造影剤を使ってCT検査が行われます。
5)超音波内視鏡検査(EUS)
超音波プローブをつけた内視鏡を口から入れて、胃や十二指腸から膵臓の病変を確認する検査です。必要であれば病変に針を刺して組織を採取する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)を行うこともあります。
6)内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)
口から内視鏡を入れて十二指腸まで進め、膵管と胆管の出口にある十二指腸乳頭に細い管を通して造影剤を注入し、X線撮影をする検査です。同時に膵管内の細胞を採取する膵液細胞診検査が行われることもあります。急性膵炎などの合併症を起こすこともあるため、他の検査で診断が確定しない時などに行われます。
7)病理検査
EUS-FNAやERCP検査などで採取された組織を顕微鏡を使って確認し、悪性のものなのかどうかや、がんの性質を確定するための検査です。
8)PET検査
がんがブドウ糖を取り込む性質を利用し、ブドウ糖に似た薬剤を注射して薬剤の取り込みの分布を撮影してがんの広がりを調べる検査です。膵臓がんでは疑いの状態ではPET検査は実施せず、膵臓がんと確定してから他臓器への転移などを確認する目的で行われます。
9)審査腹腔鏡検査
全身麻酔でおなかに小さな穴を開け、腹腔鏡を挿入しておなかの中を観察します。肝転移や腹膜播種が疑われる時に行われることがあります。
お問い合わせ先
NPO法人日本統合医療推奨協会では、フコイダン療法やがん統合医療についての無料相談窓口を設置しております。
臨床に基づいた飲用方法、がん治療についてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。
お電話が繋がらない場合は、氏名・ご連絡先・お問い合わせ内容をご入力の上info@togoiryou.comまでメール送信下さい。
資料もご用意しております。
フコイダン療法についての無料レポートをご用意しております。お電話または資料請求フォームよりご請求下さい。